題名に、人が!人類が!!答えを渇望するものがどどーんとありますが
私は、本書で紹介されていることに
まさに、これだよ!この言葉が欲しかったんだよという思いと同時に
人類の永遠の問いなんだなという思いを同時に感じました。
人が人であり続ける以上、生と死はつきもので
そのことについて考えずにはいられない
その考えた先の答えが出ないことへの
アンサーというか、きっかけになると私は信じています。
早速、私が感じたことを紹介していくよ!!
概要
まずこの本の概要について引用させていただきました。
なぜ私たちは悩みや不安からいつまでたっても解放されないのか。
それは「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」という問いに答えられないために、一つひとつの悩みの根底にある「漠然とした不安」が解消されないからではないか。
精神科医である著者が、この問いに初めて向き合ったのは10歳のとき。それから40年経った今、この問いに実践レベルで答えが出せるのは仏教しかないと著者は確信し、日常の中でその教えを実践している。
何も出家などしなくとも、誰でも実践できる「行」や「方便」によって、曇りない心で真実をつかみ、毎日を明るく生きられるようになるのである。「行」とは日々の行動習慣の一種だが、「背筋を伸ばす」「眼鏡を拭く」「朝、シャワーを浴びる」といったことでも「行」になる。「方便」はごく簡単に言えば「困っている人に親切にする」ということであり、人間関係のつまらない行き違いをなくすためにも必要な姿勢である。Amazonの商品説明より抜粋
どうせ死ぬのになぜ生きるのか?
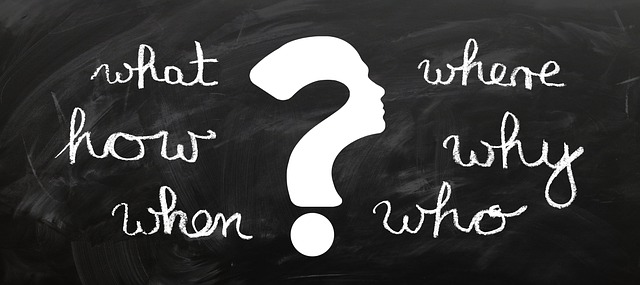
早速結論から話すのですが、どうせ死ぬのになぜ生きるのか?
この本書では、、、、
私の口からは、お話できないので手に取っていただきたいのですが、、
話せることだけ話すと、、、
言葉で説明できることには限界がある

ということですね。はい
人生において、解決できない問いっていくつかあると思うんです
その中の一つとして、なぜ生きるのか?があると思います
こう言った問いは、言語の先にある景色が見えないと本当の意味で
納得、理解するということには至らないのかな、、
と私としても思いました。
心は自分じゃない

文中にこの言葉が出てきます。
仏教では、「自分の心」と「自分自身」とは別のものだと明確に定義しています。拙著『自分を支える心の技法』(医学書院)の中で僕は〈「心」というのは「自分」にとって付き合いにくい隣人のような存在です〉
「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」第3章53ページ
私はこの言葉
常に私たちは、心が私自身と疑わなかったと思うんです。(私だけかもしれません)
この言葉があると、確かに、ずっとそこにあるはずのない「心」が
私自身なわけないと、言われないと気づかないんですよね
ずっと変わらないものなんてないはずなのに、、
僕たちは水面に映ったものを見ているに過ぎない

僕たちが見ているこの世の中。
全ての現象のこと
今目の前で起きたこと全てを
私たちは正しく見ることはできないと言っています。
これって水面に映ったものを一生懸命見ようとしているような
ものだと私は思いました。
だったら、どうやったらこの水面に映ったものをクリアに
しっかり見ることができるのか?
この答えも、この本に書かれています。
ぜひ皆さんもお手に取っていただければと思います。
私の感想

正直まだ、言いたいことたくさんあるんですが、
普段これってどういうことなんだろう?
生きていて、答えのない問いに苦しめられることって多々あると思うんです
それこそ、自分てなんだろう?この問いの答えって一応用意されているけど
骨の髄までわかっていて納得している人ってどれくらいるんでしょうか?
こんな時代だからこそ、これまでの先人が培ってきた知恵や習慣に突破口が
この本や仏教というところに眠っているのかな?と思いました。
それじゃあ、またね
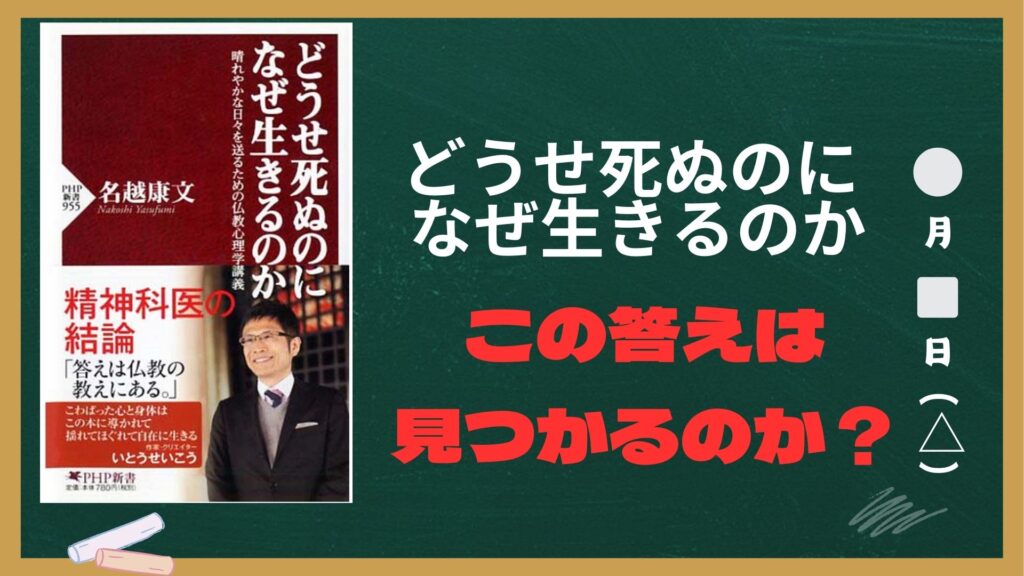


コメント